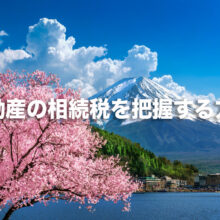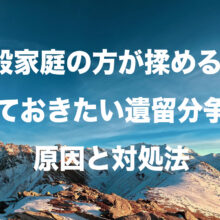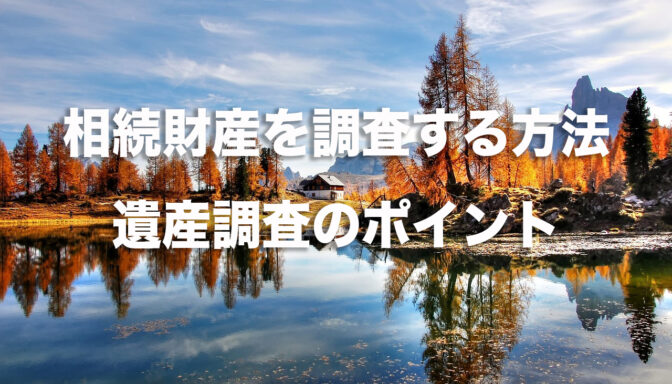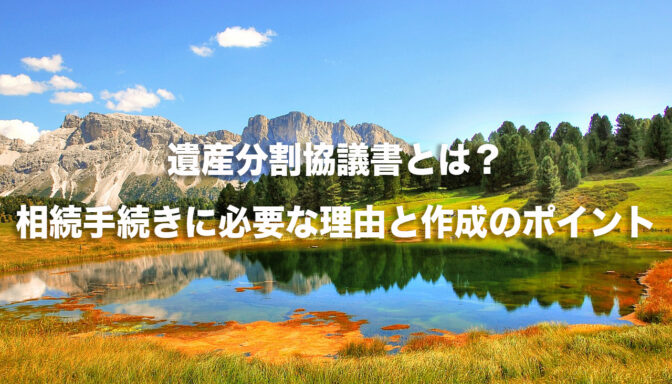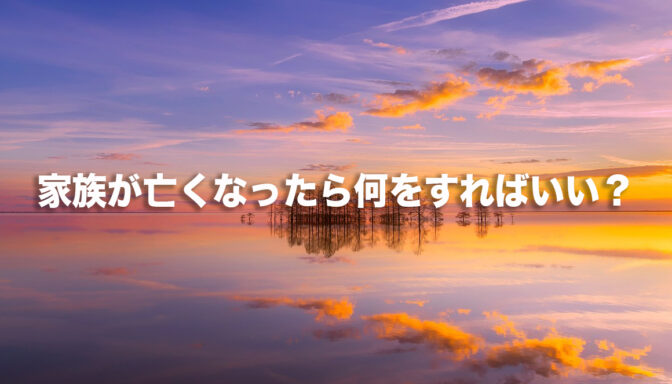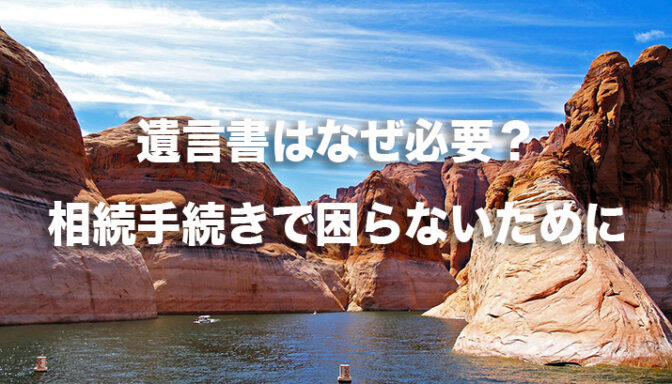家族信託(民事信託)は、認知症対策や資産承継の手段として非常に有効ですが、信託を設定した後に何もしなくてよいわけではありません。受託者には、信託財産の管理・運用に関するさまざまな義務があります。
本記事では、受託者が随時行うべき業務や年次報告の義務、税務申告について詳しく解説します。信託契約を適切に履行し、スムーズな財産管理を行うためのポイントを確認しましょう。
受託者が随時行うこと
受託者は、信託契約書の内容に基づき、以下の管理業務を行います。
- 信託財産の管理(預貯金、不動産、有価証券など)
- 信託財産の帳簿記録
- 通帳の記帳・管理
- 現金出納帳の作成
- 領収書・レシート・契約書などの保存(最低10年間)
- 不動産の管理・処分(売却や賃貸契約の締結など)
- 受益者への金銭給付(信託契約に定められた金額の振込など)
特に、賃貸物件を信託した場合は、信託前と同程度の帳簿作成が求められます。税務処理を適切に行うためにも、必要に応じて税理士に相談しましょう。
受託者が年に1回行うこと
1. 財産管理報告(受益者への報告)
- 12月31日付で「貸借対照表・損益計算書」等を作成
- 財産目録、通帳記録、現金出納帳などとともに受益者へ報告
2. 税務申告(税務署への届出)
- 信託財産に関する収益が 3万円以上(計算期間が1年未満の場合は1.5万円以上) の場合、
- 1月31日までに「信託の計算書及びその合計表」を税務署へ提出
- 収益がなければ申告不要
信託に関する税務処理は複雑になることが多いため、税理士に依頼するのが安心です。
確定申告を行う
受託者は、信託財産から生じた収益(賃料収入や不動産売却益など)について、受益者の代理として確定申告を行う必要があります。
- 収益があった場合 → 受益者名義で確定申告を実施
- 単発の不動産売却など → 自身で申告可能だが、税理士への相談推奨
相続が発生した場合の対応
1. 受益者が亡くなった場合
受益者が亡くなると、信託を「終了」または「継続(受益権の承継)」のいずれかを選択する必要があります。
【信託を終了する場合】
- 受託者は信託財産を帰属権利者へ譲渡
- 翌月末までに「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及びその合計表を税務署へ提出
- 不動産の所有権移転登記および信託登記の抹消
- 債権・債務の整理と弁済
- 帰属権利者が相続税申告を行う場合あり
【信託を継続する場合】
- 第2受益者が受益権を承継
- 翌月末までに税務署へ「受益者別(委託者別)調書」を提出
- 不動産を信託している場合は、登記簿の信託目録の変更登記が必要な場合あり(司法書士へ相談推奨)
2. 受託者が亡くなった場合
受託者が亡くなった場合、信託契約書に指定された次の受託者が信託財産を引き継ぎます。
- 新たな受託者がいない状態が1年間続くと、信託は強制終了
- 不動産の所有権移転登記が必要(司法書士へ相談)
- 信託口座がある場合、新たな受託者へ引き継ぐため金融機関へ連絡
3. 信託監督人・受益者代理人が亡くなった場合
- 信託契約書の指定に従い、新たな監督人・代理人を選任
- 不動産信託がある場合は、登記簿の変更登記が必要になる可能性あり(司法書士へ相談)
まとめ
家族信託は、相続対策や認知症リスクに備える有効な手段ですが、信託組成後も受託者には多くの義務があります。特に、財産管理や税務申告、受益者の変更時の手続きには注意が必要です。
信託の適切な運用には、税理士や司法書士などの専門家と連携することをおすすめします。家族信託を正しく活用し、スムーズな財産承継を実現しましょう。