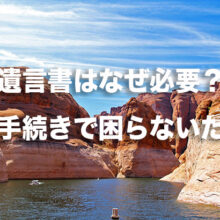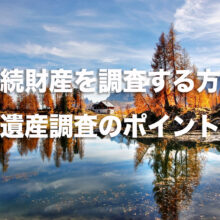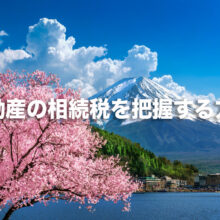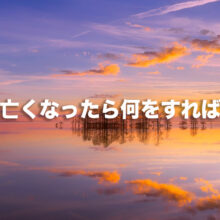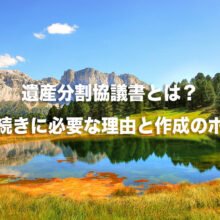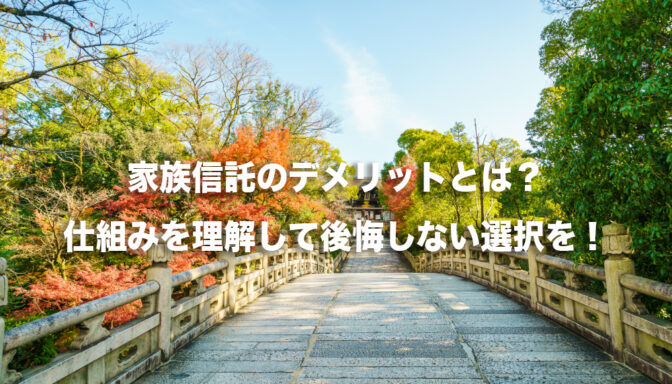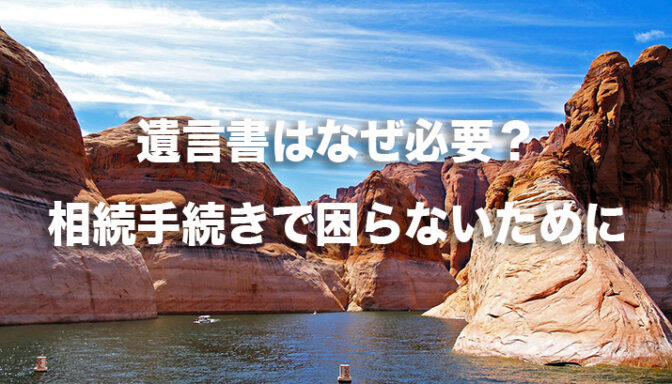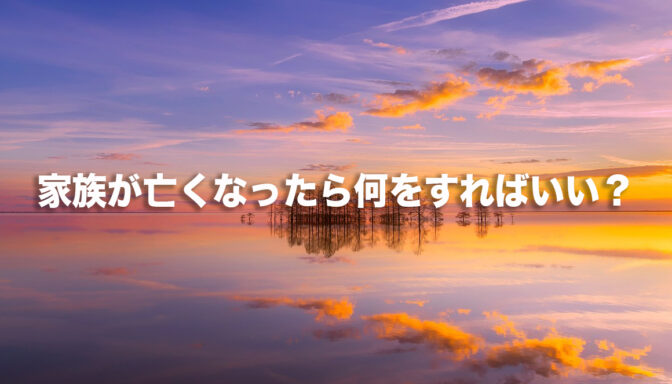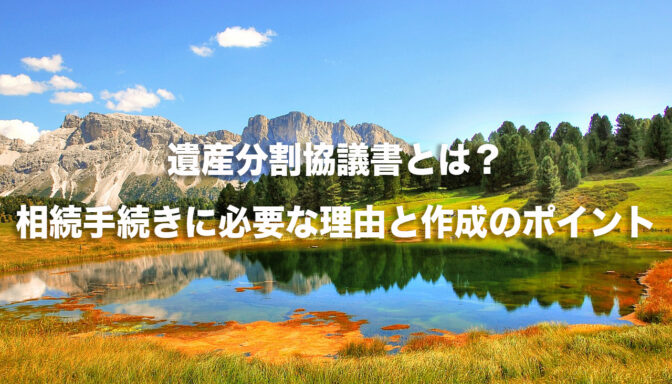はじめに
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
「遺言書を書きたいけれど、どう書けばいいかわからない…」
そんな方のために、公正証書遺言の作り方や必要書類、費用について詳しく解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される遺言書のことです。
📌 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証役場で公証人が関与 | 自分で手書きする |
| 無効のリスク | ほぼなし | 書き方を間違えると無効になる可能性あり |
| 紛失のリスク | なし(原本が公証役場に保管) | 紛失・改ざんの可能性あり |
| 検認手続き | 不要 | 家庭裁判所で検認が必要 |
公正証書遺言は手間や費用がかかりますが、確実性が高く、相続手続きがスムーズに進むためおすすめです。
公正証書遺言の作成手順
1. 公証役場または専門家に相談
まずは、公証役場や行政書士・司法書士などの専門家に相談しましょう。
✅ 遺言の内容を整理する ✅ 遺言書に必要な情報を確認する ✅ 証人2人を用意する(※公証役場で手配も可能)
2. 必要書類の準備
🔹 人物関係の書類
- 遺言者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 遺言者の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺贈を受ける人の住民票
🔹 不動産関連の書類
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書、名寄帳
🔹 金融資産関連の書類
- 通帳のコピー(口座情報、残高がわかる部分)
- 株、国債、投資信託などの資料
- 保険関連資料(※死亡保険金は遺言書への記載不要)
3. 遺言内容の確認・打ち合わせ
公証役場の公証人と打ち合わせを行い、遺言の内容を決定します。
📌 証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
士業に依頼している場合、証人を手配してもらえるケースもあります。
4. 公正証書遺言の作成・署名
- 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述
- 公証人が遺言書の原稿を作成
- 公証人が遺言内容を読み上げ確認
- 遺言者・証人が署名押印(遺言者は実印)
- 公証人が署名押印
- 手数料を支払い、公正証書遺言の正本・謄本を受け取る
✅ 正本 … 原本と同じ効力を持つ書類 ✅ 謄本 … 原本の写し
金融機関の手続きでは正本が必要な場合があるので、大切に保管しましょう。
公正証書遺言の費用
公証役場での公正証書遺言作成には、以下の手数料がかかります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 43,000円 + 超過額5000万円ごとに13,000円加算 |
| 3億円超~10億円以下 | 95,000円 + 超過額5000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 249,000円 + 超過額5000万円ごとに8,000円加算 |
📌 公正証書の枚数や正本・謄本の交付数によって手数料が加算される場合があります。詳しくは公証役場でご確認ください。
まとめ
公正証書遺言は、確実性が高く、相続手続きをスムーズに進めるための最適な方法です。
✅ 形式ミスによる無効のリスクがない
✅ 家庭裁判所の検認手続きが不要
✅ 公証役場に保管されるため紛失の心配がない
「遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不安…」という方は、公正証書遺言の作成を検討してみてください。
遺言書の作成サポートについては、ぜひ専門家にご相談ください!