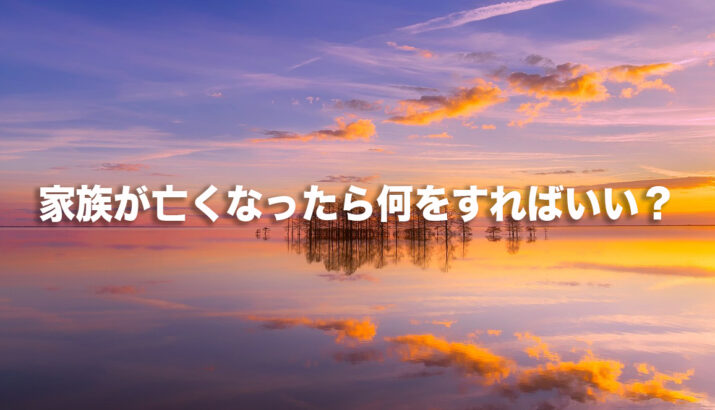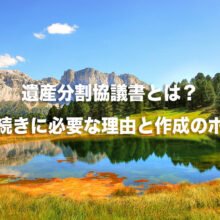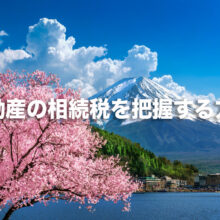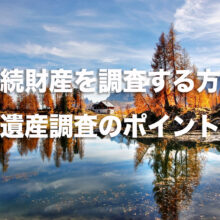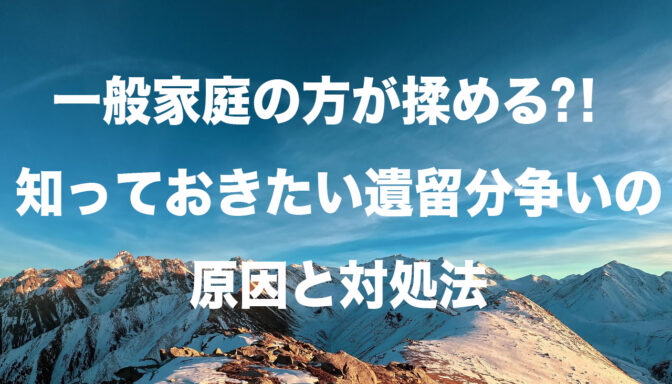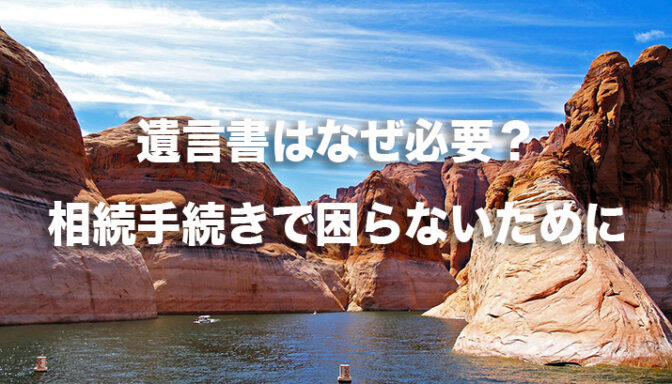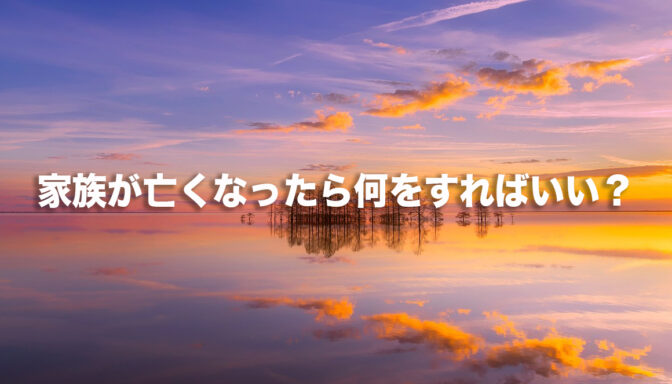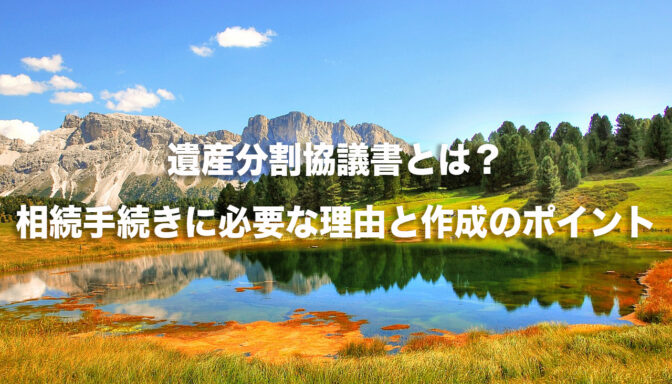はじめに
家族が亡くなったとき、悲しみに浸る間もなく、葬儀の手配や親族への連絡など、多くの手続きが必要になります。さらに、1週間から2週間以内に行わなければならない役所への届出や手続きがあり、慌ただしく時間が過ぎていきます。
この記事では、家族が亡くなった後に必要な手続きを時系列で整理し、スムーズに対応できるようポイントを解説 します。
亡くなった後に必要な主な手続き(2週間以内)
1. 死亡診断書の受け取り
亡くなった際に医師が作成する書類です。
- 病気や老衰の場合 → 「死亡診断書」 を医師が発行。
- 事故や事件の場合 → 「死体検案書」 を医師が作成。
この診断書は、死亡届の提出時に必要になるため、原本を大切に保管し、必要に応じてコピーを取っておきましょう。
2. 死亡届の提出(7日以内)
- 届出人:親族、同居人、家主、後見人 など
- 提出期限:死亡後7日以内
- 提出先:亡くなった人の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市区町村役場
※ 提出前にコピーを数枚取っておくと、今後の手続き(保険・年金など)で役立ちます。
3. 火葬許可申請の提出
死亡届と同時に火葬許可申請書を役所へ提出し、火葬許可証を取得します。多くの場合、葬儀会社が代行してくれる ので、確認しておきましょう。
火葬~納骨までの流れ
- 死亡届・火葬許可申請の提出
- 火葬許可証の交付
- 火葬場で火葬許可証を提出
- 埋葬許可証の交付
- 納骨時に埋葬許可証を提出
各種手続きの詳細(14日以内)
1. 世帯主の変更(世帯主が亡くなった場合)
- 提出期限:14日以内
- 提出先:亡くなった人の住所地の市区町村役場
- 持参するもの:世帯員の健康保険証(国民健康保険加入者の場合)
2. 健康保険の資格喪失届
国民健康保険加入者の場合
- 提出期限:14日以内
- 提出先:市区町村役場
- 返却するもの:国民健康保険証、高齢受給者証(75歳以上は後期高齢者医療保険証)
- 必要書類:死亡を証する書類(戸籍謄本など)、届出人の本人確認書類、印鑑
後期高齢者医療の対象者だった場合
- 医療費が戻る可能性があるため、高額療養費の支給申請 を行う。
- 限度額適用・特定疾病療養受給者証を持っていた場合は、返却が必要。
会社員や公務員の場合(健康保険組合加入者)
- 提出期限:5日以内
- 提出先:年金事務所
- 会社が手続きを代行する場合が多いため、まずは会社に相談 しましょう。
3. 介護保険の資格喪失届
- 提出期限:14日以内
- 提出先:市区町村役場
- 返却するもの:介護保険被保険者証
4. 年金受給停止の手続き
- 国民年金:14日以内に「年金受給者死亡届」を提出。
- 厚生年金:10日以内に「年金受給者死亡届」を提出。
- 提出先:年金事務所または年金相談センター
※ 未支給年金の請求、遺族年金の受け取りは時効が5年までなので注意!
その他の手続き
上記の手続きが落ち着いたら、公共料金の停止、銀行口座や財産の名義変更 などの手続きを進めましょう。
主な手続き一覧
- 公共料金(水道・電気・ガス・電話・インターネット)の名義変更または解約
- クレジットカードの解約
- 銀行口座の解約・名義変更
- 自動車や不動産の相続手続き
- 保険の請求(生命保険、医療保険 など)
手続きが多くて不安な方は、専門家(行政書士・司法書士)に相談するのも一つの方法です。
まとめ
家族が亡くなった後は、多くの手続きを迅速に行う必要があります。特に死亡届、健康保険・年金の手続き、火葬許可申請 などは期限が短いため、早めに対応しましょう。
相続や名義変更に関する手続きは専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
大切な人を失った後の負担を少しでも減らすために、この記事が参考になれば幸いです。