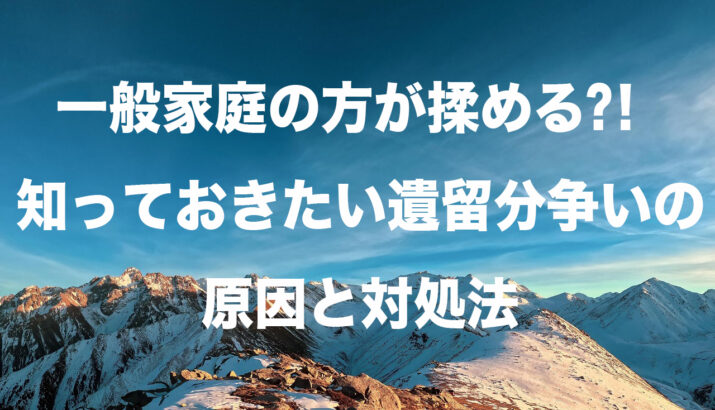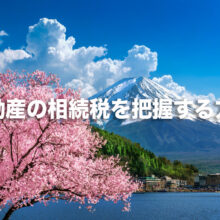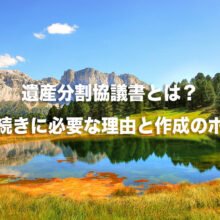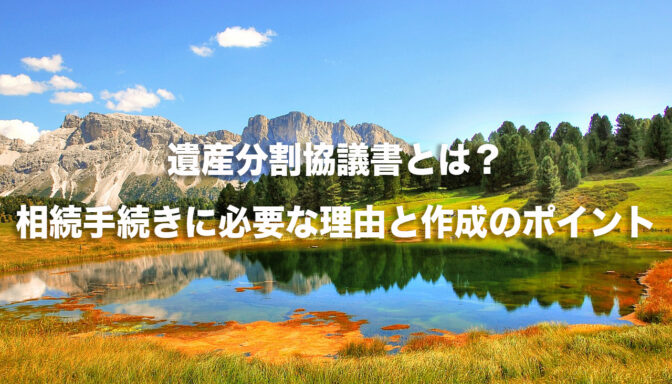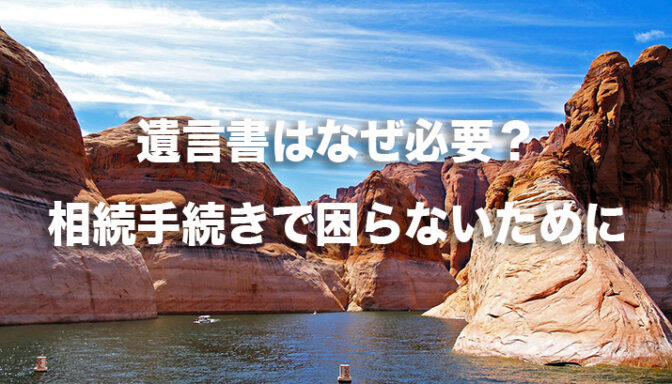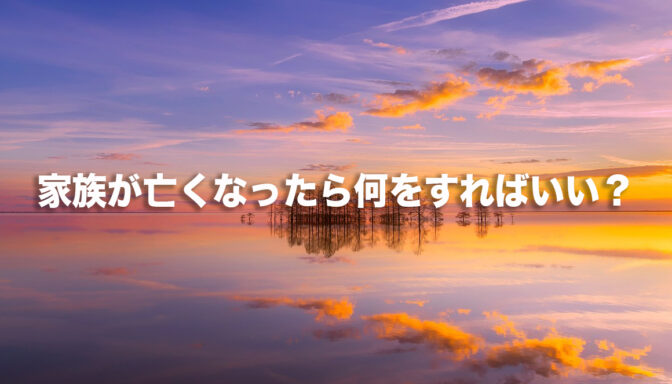はじめに
相続争いと聞くと、ドラマなどで見るような「資産家同士の骨肉の争い」をイメージしがちではないでしょうか?
実は、相続トラブルの多くは資産額3,000万円以下の一般家庭で発生している というデータがあります。
では、なぜ相続争いが起きるのでしょうか?
今回は、特に「遺留分争い」に焦点を当て、その原因と対策について詳しく解説していきます。
遺留分とは?
遺留分とは、特定の相続人が最低限の相続財産を確保するための権利 です。
例えば、亡くなった方(被相続人)が「全財産を特定の相続人や第三者に相続させる」という遺言書を残した場合、他の相続人が何も相続できなくなる可能性があります。
しかし、遺留分を主張することで、最低限の相続財産を金銭で請求することが可能 になります。
遺留分争いが起こるケース
例えば、以下のようなケースでは遺留分争いが発生しやすくなります。
- 特定の相続人に全財産を相続させる遺言書がある場合
例:「長男に全財産を相続させる」など - 愛人や特定の第三者に財産を遺贈した場合
例:「○○さん(内縁の妻)に全財産を譲る」など - 生前贈与で特定の相続人に大きな財産を与えていた場合
例:「長男がすでに実家をもらっている」など
遺言書の内容が偏っていると、他の相続人が不満を持ち、遺留分を主張する可能性が高くなります。
遺留分の計算方法
遺留分は、法定相続分の1/2 です。
例えば、母が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だった場合を考えます。
法定相続分は長男・長女それぞれ 1/2 ですが、遺留分はその 1/2(=1/4) になります。
具体例
- 母の財産が 2,000万円 だった場合
- 遺言で「長男に全財産を相続させる」と書かれていた場合
- 長女の遺留分は 500万円(2,000万円 × 1/4) となる
- 長女は長男に 500万円を請求できる(遺留分侵害額請求)
遺留分を請求できる人
遺留分を主張できるのは、以下の相続人です。
✅ 配偶者(夫・妻)
✅ 子ども(直系卑属)
✅ 両親(直系尊属)※子どもがいない場合のみ
⚠ 亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の請求手続き
1. 相続が発生したらまず遺言書の確認
遺言書がある場合、その内容を確認し、自分の遺留分が侵害されているかを判断します。
2. 遺留分侵害額請求をする
遺留分を侵害されている場合、財産を相続した人に対して請求 します。
この請求は 相続開始を知った日から1年以内 に行う必要があります。
📌 具体的な手順 ✅ 内容証明郵便 で請求する(証拠を残すため)
✅ 交渉が成立すれば、支払いを受ける
✅ 交渉が決裂した場合は、家庭裁判所で 遺留分侵害額請求調停 を申し立てる
⚠ 1年以内に請求しないと、遺留分の権利が消滅するので注意!
遺留分争いを防ぐための対策
遺留分争いを防ぐには、生前の対策が重要 です。
✅ 1. 公正証書遺言を活用する
公正証書遺言を作成し、遺留分の権利を考慮しながら、相続人に納得してもらえる内容にする。
✅ 2. 生命保険を活用する
生命保険の 死亡保険金は遺産分割の対象外 となります。
特定の相続人に多くの財産を渡したい場合、生命保険を活用するとスムーズに分配できます。
✅ 3. 生前贈与で調整する
生前に贈与しておくことで、相続時のトラブルを回避できる場合があります。
ただし、贈与税や「特別受益」の問題があるため、計画的に行うことが重要です。
まとめ
相続争いは 資産家だけでなく、一般家庭でも起こり得る問題 です。
特に 遺留分争いは、財産の偏った相続が原因で発生しやすい ため、事前の対策が大切です。
🔹 遺言書を適切に作成する
🔹 生命保険などを活用して財産を分配する
🔹 遺留分侵害額請求の期限(1年)に注意する
「うちには関係ない」と思わずに、早めに相続対策を考えてみましょう!