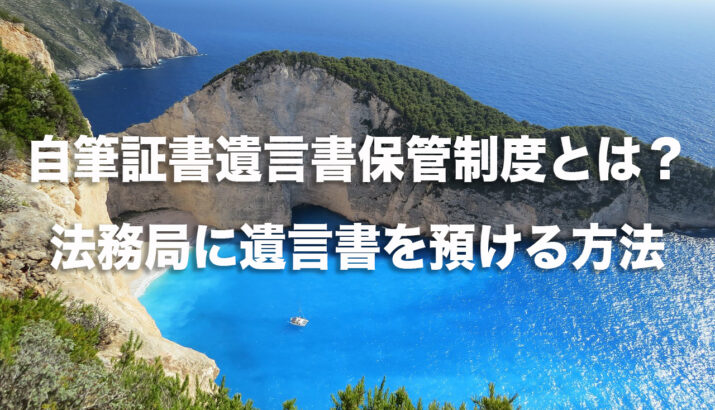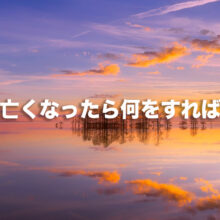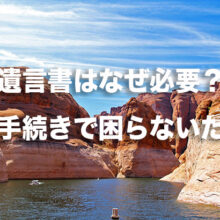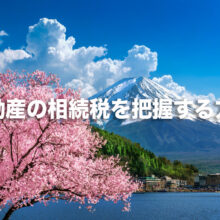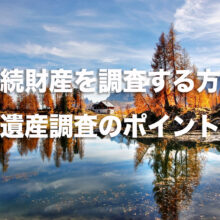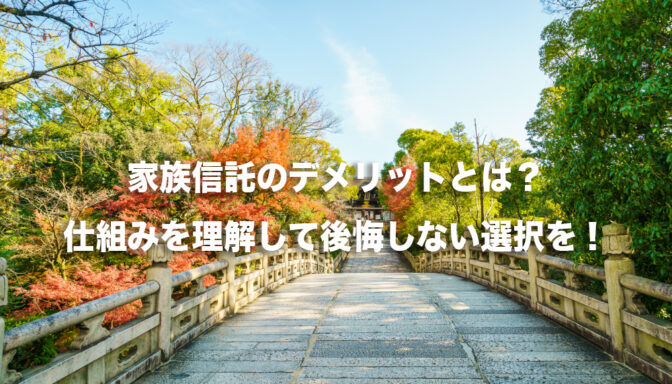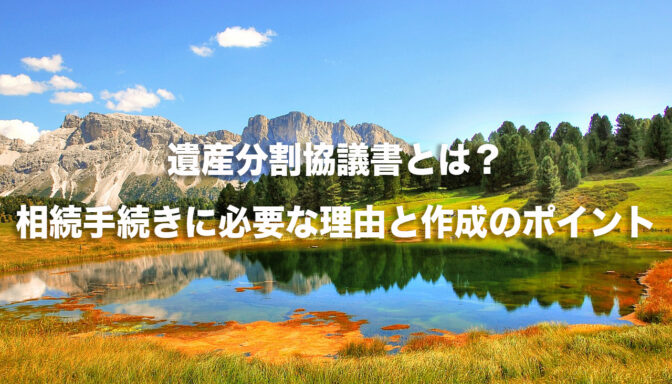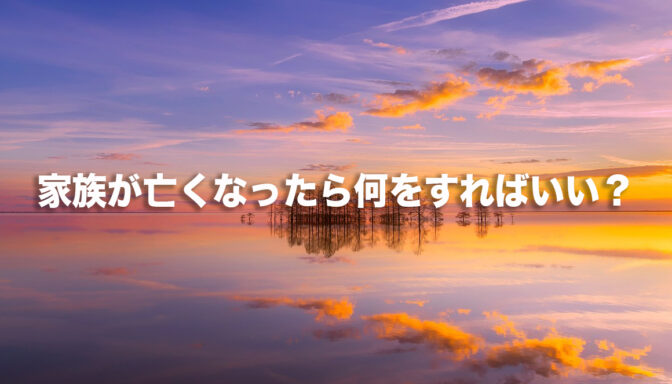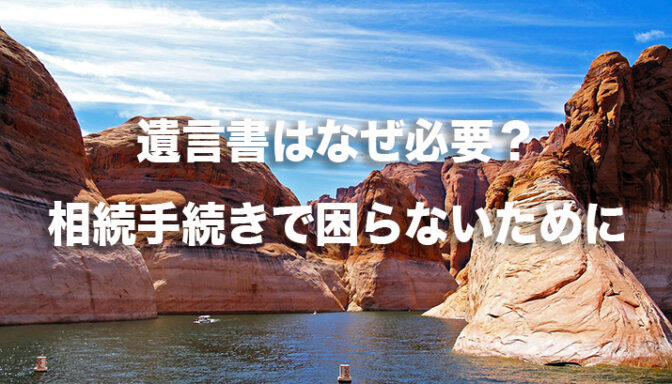はじめに
せっかく書いた遺言書を紛失したり、悪意のある相続人によって隠されたりするリスクをご存知でしょうか?
2020年7月10日から、法務局で遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
今回は、相続のトラブルを防ぐために法務局に遺言書を預ける方法 について詳しく解説します。
自筆証書遺言の問題点
自筆証書遺言は自宅で作成されることが多く、そのまま自宅で保管されるケースがほとんどです。しかし、この場合には以下のリスクが伴います。
- 遺言書を紛失してしまう可能性がある
- 相続人の誰かが遺言書を隠す、改ざんする、廃棄するリスクがある
- 遺言書の存在が知られずに、相続手続きが進められてしまう可能性がある
一言で言えば、適切な保管をしないと相続トラブルの原因になりかねないということです。
法務局に保管すると何が変わるのか?
これらの問題を解決するために設けられたのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。
- 法務局が遺言書の原本を保管し、紛失や隠匿を防ぐ
- 遺言書を画像データ化し、いつでも確認できる
- 相続が開始した際に、相続人は法務局で「遺言書情報証明書」を取得可能
- 家庭裁判所の検認手続きが不要 になる
- 遺言書の交付請求があった場合、他の相続人にも通知が届く
法務局による自筆証書遺言書保管制度のメリット
✅ 遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防げる
✅ 遺言書の存在が相続人に通知されるため、もめ事を防げる
✅ 家庭裁判所の検認手続きが不要
✅ 全国どこからでも照会可能(保管された法務局に行く必要なし)
遺言書保管の申請方法
1. 自筆証書遺言を作成する
法務局に預ける自筆証書遺言には、以下のルールがあります。
- A4サイズの紙を使用
- 文字が読みづらくなるような地紋や彩色がない紙を使う
- 余白を確保する(左20mm以上、上5mm以上、右5mm以上、下10mm以上)
- ホッチキス止めは禁止
- 各ページに「1/3」「2/3」などのページ番号を記載
- 本文はすべて自書(直筆)
- 財産目録はパソコン作成可だが、全ページに署名押印が必要
2. 遺言書を保管する法務局を決める
以下のいずれかの管轄の法務局を選びます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
📌 管轄法務局の確認はこちら → 法務局の公式サイト
3. 申請書を作成する
遺言書保管所(法務局)に行く前に、遺言書の保管申請書 を作成します。
📌 申請書のダウンロードはこちら → 法務省の公式ページ
4. 保管申請の予約をする
申請書が完成したら、法務局に電話で予約 します。
予約時に、氏名・住所・生年月日・連絡先などを伝えます。予約番号や必要な持ち物の案内があるので、忘れずにメモしておきましょう。
5. 保管申請をする(本人のみ手続き可能)
予約日時に遺言者本人が法務局へ行き、以下の書類を提出します。
📌 持ち物
- 遺言書(ホッチキス止め・封筒不要)
- 申請書
- 本籍記載の住民票(発行3か月以内)
- 本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 収入印紙3,900円分
所要時間は約30分~1時間程度で、「保管証」が交付されます。
📌 保管証には何が書かれている?
✅ 遺言者の氏名・生年月日
✅ 遺言書保管所(法務局)の名称
✅ 保管番号(重要!)
保管番号を家族と共有すると、相続発生時の手続きがスムーズになります。
法務局による自筆証書遺言書保管制度の注意点
この制度は非常に便利ですが、財産目録以外はすべて手書き で作成しなければならないため、内容が複雑な場合は適していません。
✅ 複雑な遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言の方が向いています。
遺言書作成で行政書士に頼めること
🔹 遺言書の作成アドバイス
🔹 遺言の執行
🔹 財産目録の作成
🔹 相続人の調査
🔹 相続関係図の作成
🔹 戸籍の取得
まとめ
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書の紛失や隠匿のリスクを防ぎ、相続トラブルを回避できます。
✅ 遺言書を適切に保管し、家族に負担をかけない準備を進めましょう。
相続や遺言書作成についてお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。