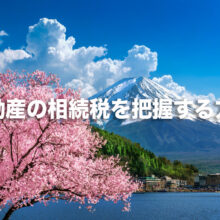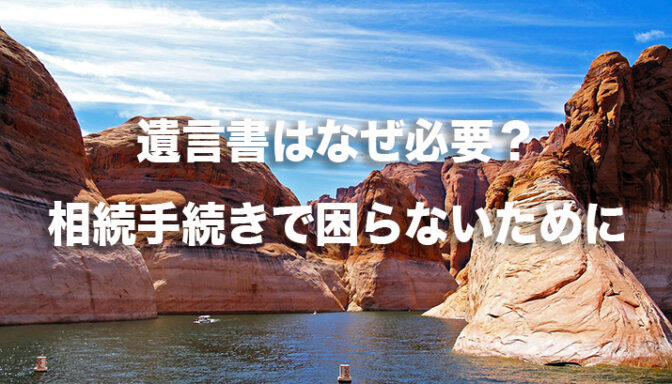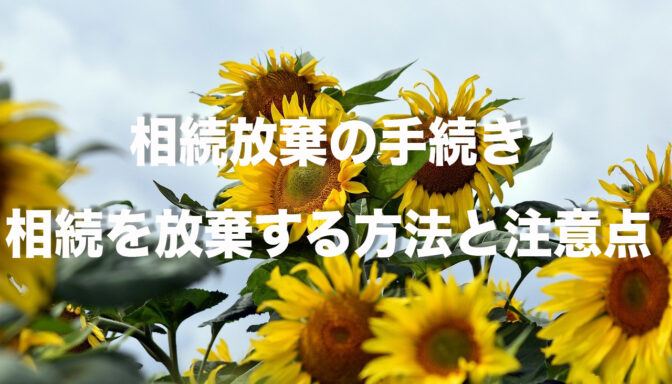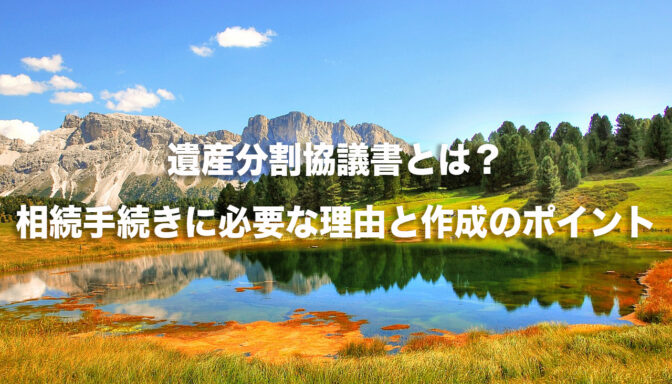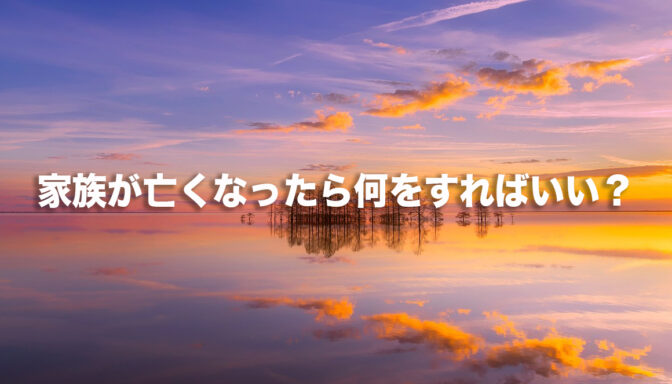相続財産の中でも、不動産が占める割合は非常に大きいケースが多いです。
現金や預貯金は額面通りに評価されるため分かりやすいですが、不動産の場合、評価方法が複数存在し、どの計算方法を使えばよいのか迷う方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の相続税評価額を簡単に把握する方法をご紹介します。
まず前提として、正確な相続税評価額を算出するには専門的な知識が必要です。しかし、おおよその評価額を知ることで、相続税が発生するのかどうかを判断でき、事前の対策もしやすくなります。
土地の相続税評価額の計算方法(3つの方法)
土地の相続税評価額を知るには、以下の3つの方法があります。
① 固定資産税評価額から算出する方法(簡易的な計算)
もっとも手軽に土地の相続税評価額を把握する方法が、固定資産税評価額を基に計算する方法です。
毎年4~6月頃に届く固定資産税通知書に記載された「評価額」の数値を使い、以下の計算式で概算額を求めます。
計算式
固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 0.8 = 相続税評価額例
固定資産税評価額が3,000万円だった場合
3,000万円 ÷ 0.7 × 0.8 = 約3,428万円この3,428万円が、その土地のおおまかな相続税評価額となります。
② 地価マップを活用する方法(路線価を一発で確認)
「相続税の基準となる路線価を一発で見られる便利なサービス」が存在します。
📌 地価マップ(Chikamap)
(住所を入力するだけで、該当地の路線価を確認可能)
このサイトで該当の土地を検索し、面している道路に書かれている数字(例:135)を探してください。
例えば「135」と書いてあれば、1㎡あたり135,000円の評価額ですよ、という事になります。
計算式
路線価(1㎡あたりの評価額) × 土地面積(㎡) = 相続税評価額例
- 路線価:135千円(1㎡あたり)
- 土地面積:100㎡
135,000円 × 100㎡ = 1,350万円この計算で、土地の相続税評価額がざっくりと把握できます。
補足:土地面積が分からない場合
土地の面積が不明な場合、Googleマップの「距離を測定」機能を活用すれば、大まかな面積を計測できます。
グーグルマップで対象の場所で右クリックすると、「距離を測定」という機能が出てきますので、なんとこれで対象地を囲むとだいたいの面積が計測できてしまうんです。
③ 路線価図(国税庁)を活用する方法
📌 国税庁 路線価図
(地図上から路線価を確認可能)
この方法は地価マップと違い、住所を直接検索できないため、地図を手動で読み取る必要があります。やや手間がかかるため、②の地価マップの方が使いやすいでしょう。
土地の相続税評価額を補正するポイント
上記の3つの方法で算出した金額は「額面評価額」であり、以下の条件によって減額調整が可能です。
✅ 旗竿地(間口が狭く奥に長い土地)
✅ セットバック(道路後退が必要な土地)
✅ 線路沿い・崖地などの不利な立地
✅ 小規模宅地等の特例(相続税を最大80%減額)
こうした減額が適用できる場合があるため、正確な評価額を知りたい方は税理士や相続の専門家に相談することをおすすめします。
建物の相続税評価額(計算方法)
建物の相続税評価額の算出方法は、非常にシンプルです。
固定資産税通知書に記載されている評価額=相続税評価額 となります。
📌 固定資産税通知書が手元にない場合
- 市区町村の役場で「評価証明書」を取得すれば確認可能
これで、土地と建物の評価額が分かれば、不動産全体の相続税評価額が把握できます。
まとめ:不動産の相続税評価額を把握して、早めの対策を!
✅ 土地の相続税評価額は「固定資産税評価」「地価マップ」「路線価図」で概算可能
✅ 建物の相続税評価額は「固定資産税通知書」に記載の金額をそのまま使用
✅ 実際の評価額は減額補正が適用される場合があるため、専門家に相談するのがベスト
「うちの不動産、相続税かかるのかな?」と思ったら、まずは今日ご紹介した方法で概算を計算してみてください。
もし相続税が発生しそうなら、早めに対策を検討することをおすすめします。