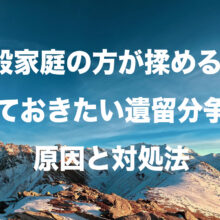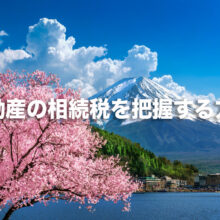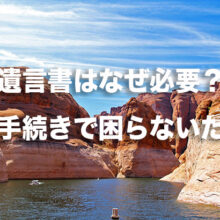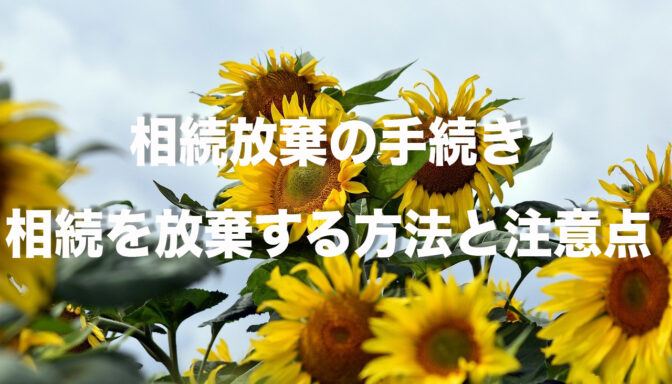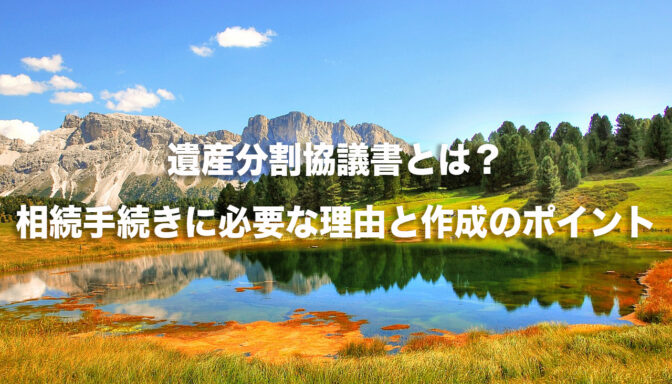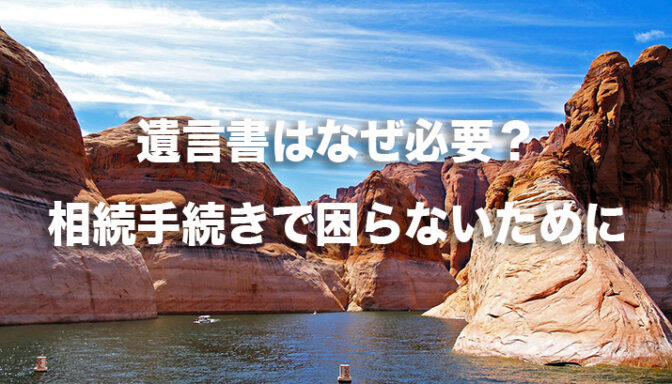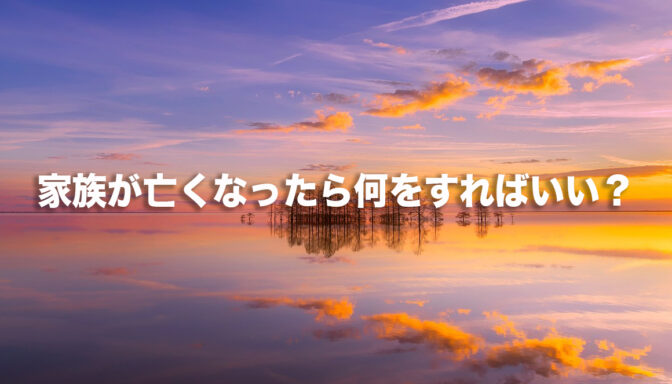はじめに
相続が発生した際、亡くなった方の財産をどのように分けるのかを話し合うのが 遺産分割協議 です。
相続が発生してから、相続税の申告期限 である10か月以内にこの協議を終え、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この期間内に、遺族(相続人)は遺産をどのように分けるかを決めるため、しっかりと話し合いを行う必要があります。
今回は、この遺産分割協議に関する 基礎知識 を紹介します。
遺産分割の方法
遺産分割には、主に以下の4つの方法があります。
- 指定分割(遺言書に基づく分割)
- 協議分割(相続人同士で話し合う分割)
- 調停分割(協議がまとまらない場合)
- 審判分割(調停で解決できない場合)
指定分割と協議分割
遺産分割方法で最も重要なのは 遺言書の有無 です。
遺言書が存在する場合、相続人の意見よりも遺言書の内容が優先されます。
つまり、遺言書に書かれた内容が法的に強い効力 を持つため、相続人の中で一部が異なる主張をしても、原則として遺言書の内容が優先されます。
ただし、相続人全員が遺言書と異なる分割方法に合意すれば、遺言書の内容を変更することも可能です。
調停分割・審判分割
協議分割で合意が得られない場合、次に進むのは 調停分割 です。
調停分割では、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って協議を行います。
それでも決着がつかない場合は、審判分割 に移行し、最終的には裁判官が分割方法を決定します。
この場合、相続人は裁判官の決定に従わなければなりません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
相続税の申告期限は 10ヶ月以内 ですが、この期限内に遺産分割協議がまとまらないと、大きなデメリットが発生します。
小規模宅地等の特例 や 配偶者の税額軽減 などの特例が使えなくなる可能性があります。
これらの特例を利用するためには、遺産分割協議が完了し、協議書が作成されていることが条件となるため、早期の協議が重要です。
遺産分割協議が無効になるケース
遺産分割協議が無効になるケースもあります。
例えば、相続人全員が協議に参加していない場合や、一部の相続人が不正に取り決めを行った場合 は、遺産分割協議書が無効となります。
このため、必ず 相続人全員が協議に参加し、同意すること が重要です。
遺産分割協議はやり直しできる?
遺産分割協議が成立した後でも、例外的にやり直しが可能なケースがあります。
次のような状況が発生した場合には、遺産分割協議のやり直しが認められることがあります。
- 遺産分割時に 詐欺 や 錯誤 、脅迫 があった場合
- 遺産分割後に 前提条件が変更 された場合
まとめ
遺産分割協議は、相続税の申告期限までに終わらせる必要があり、遺産分割協議書の作成 は非常に重要です。
遺産分割の方法には遺言書がある場合とない場合で大きな違いがあり、相続人全員が合意することが重要です。
また、遺産分割協議が無効になるケースややり直しできるケースもあるため、事前にしっかりと協議を行い、相続人全員の合意 を得ることが必要です。
もし遺産分割でお悩みの方がいれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。