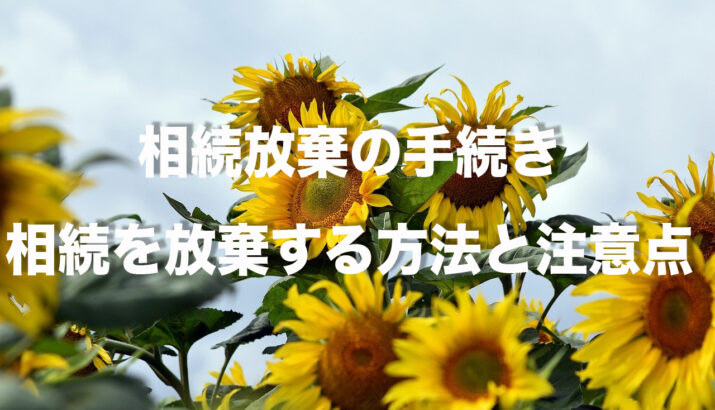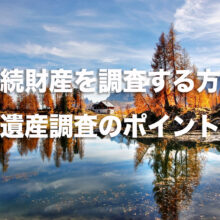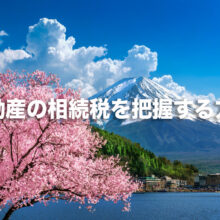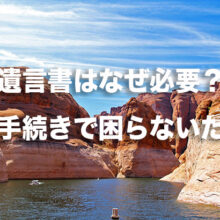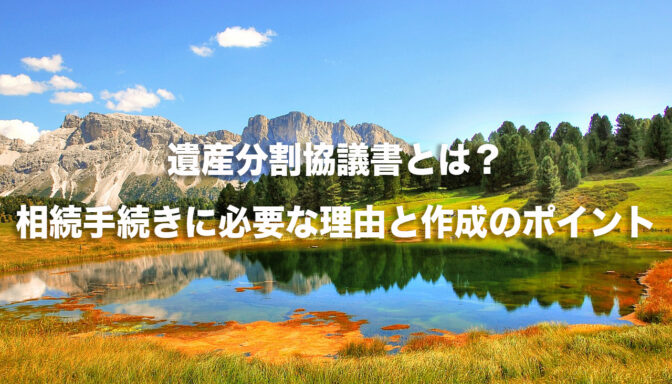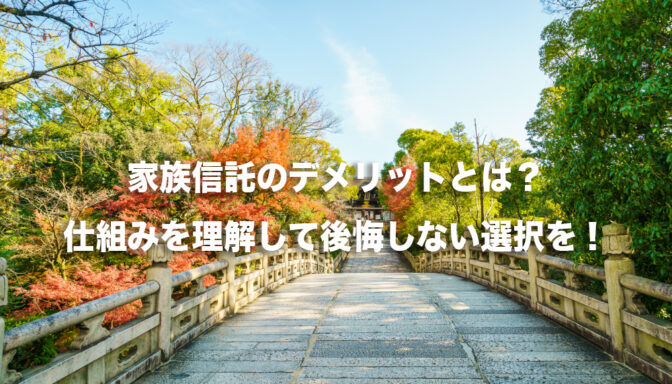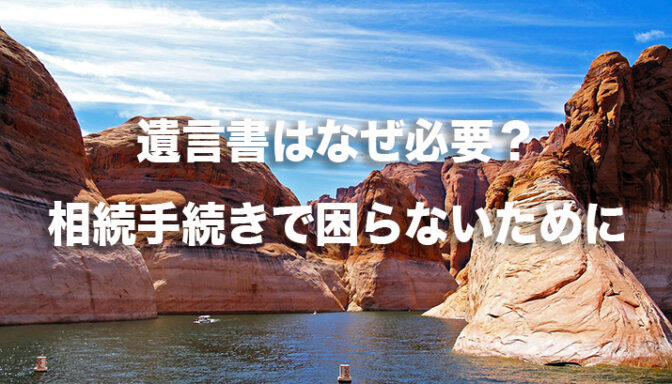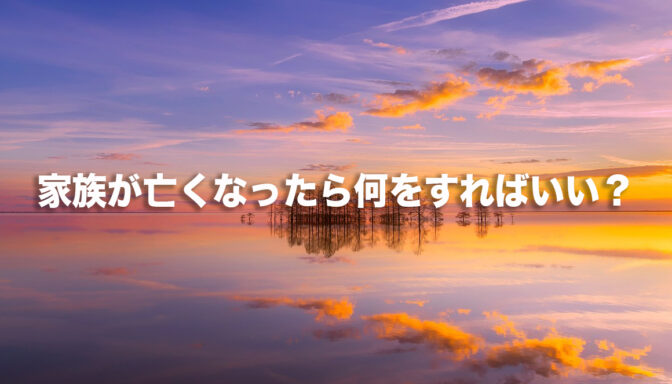はじめに
相続と聞くと「財産を受け継ぐ」というイメージが強いですが、実際には借金や負債も相続の対象になります。
「借金まで相続したくない…」そんなときに利用できるのが相続放棄の手続きです。
今回は、相続放棄の手続きの流れや必要書類、注意点 について詳しく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産(プラス・マイナス問わず)を一切受け継がない ことを意味します。
📌 重要なポイント ✅ 相続放棄をすると、借金も財産も一切受け取れなくなる
✅ 家庭裁判所での手続きが必要
✅ 手続きの期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」
相続放棄の手続きをしないままだと、亡くなった人の借金を法定相続人が返済しなければならない可能性があります。
相続放棄と遺産分割の違い
よくある誤解ですが、「遺産分割協議で財産をもらわない=相続放棄」ではありません。
❌ 遺産を受け取らなかっただけでは、借金の返済義務が残る
✅ 相続放棄の手続きをすれば、借金を含めたすべての財産を放棄できる
「財産も借金も受け取りたくない」という場合は、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを行いましょう。
相続放棄の期限と手続き
相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内 に手続きをする必要があります。
📌 3か月の期限が適用されるケース
- 亡くなった人が死亡したことを知ったとき
- 自分が相続人になったことを知ったとき
- 先順位の相続人が相続放棄をして、自分が相続人になったとき(この場合、新たに3か月の期限が始まる)
⚠ 期限を過ぎても相続放棄できる場合がある!
亡くなった人に借金がないと思っていたのに、3か月を過ぎてから突然債権者から督促が届いた場合、「借金があることを知らなかった」ことを理由に相続放棄が認められるケースもあります。
📌 この場合は証拠が必要!
債権者から届いた督促の封筒や手紙などを捨てずに保管 しておきましょう。
相続放棄でやってはいけないこと
相続放棄をしたい場合、相続財産に手をつけると放棄できなくなる ので注意が必要です。
❌ 相続放棄をする前に、以下の行為をするとNG!
- 預金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 家財道具を処分する
こうした行為をすると、「相続を承認した」と見なされてしまい、放棄が認められなくなります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をする場合、家庭裁判所に申立てを行います。
📌 手続きの流れ
- 必要書類を準備する
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
- 家庭裁判所からの「照会書」に回答し、返送する
- 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届く
📌 手続きにかかる費用 ✅ 収入印紙 800円
✅ 返信用切手(裁判所指定のもの)
✅ 相続放棄申述受理証明書(発行手数料1通 150円)
📌 申請先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続放棄の必要書類
📌 配偶者・子が相続放棄する場合
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
📌 直系尊属(親・祖父母)が相続放棄する場合
- 上記の書類に加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の子が死亡している場合、その子の戸籍謄本
📌 兄弟姉妹・甥姪が相続放棄する場合
- 直系尊属の相続放棄が完了していることを証明する書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
📌 家庭裁判所から「照会書」が送られてくるので、期日内に回答して返送しましょう。
まとめ
✅ 相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済む!
✅ 手続きは「相続開始を知った日から3か月以内」に行う
✅ 相続財産を処分すると、相続放棄できなくなるので注意
✅ 家庭裁判所に申請し、「相続放棄申述受理通知書」を取得する
相続放棄をするかどうかは、亡くなった人の財産状況をよく調査して判断しましょう。
「相続放棄をしたほうがいいのか分からない…」という方は、ぜひ専門家にご相談ください!