相続手続きの全体像と注意点:スムーズに進めるためのポイント
2025/05/01
相続手続きの基本的な流れと注意点
相続(財産を受け継ぐこと)が発生したら、まず以下のステップで手続きを進めます。初めての人でもわかりやすいように、各専門用語は具体例を交えて解説します。
目次
相続が発生した時にまずやるべき手続き
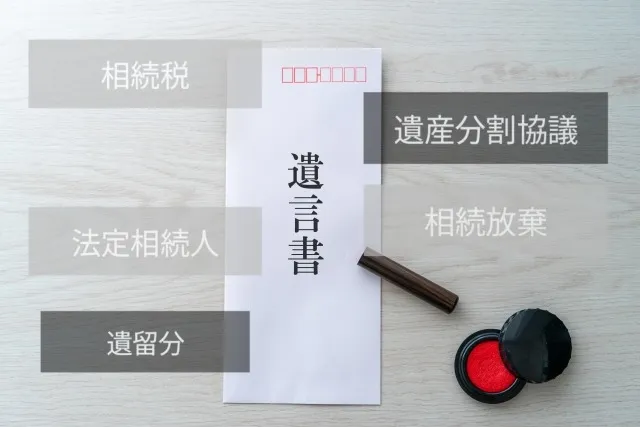
死亡の確認と必要書類の取得
親族が亡くなった(被相続人の死亡)ことを確認したら、死亡届を提出し、火葬許可証や死亡診断書を受け取ります。これらは葬儀や各種手続きで必要になる書類です。また、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで連続した戸籍)を本籍地の役所から取り寄せ、誰が法定の相続人(財産を引き継ぐ人)か確認します。例えば、被相続人が父親であれば、通常は配偶者(母親)や子どもが相続人になります。戸籍をたどることで、もし認知された子どもなど見落としてはいけない相続人がいないか確認できます。この作業を「相続人調査」といいます。

遺言書の有無の確認
次に遺言書の存在を確認します。遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」という手続きを受けます。検認とは、遺言書の内容を確認・保存するための手続きで、封を開ける前に裁判所で行います。ただし、公証役場で作成された公正証書遺言や、法務局に預けられた自筆証書遺言の場合は検認不要です。例えば、自宅から封をされた遺言書が見つかったら、すぐ開けずに家庭裁判所に持って行ってください。なお、遺言書に書かれた内容が法律上有効であれば、その指示に従って遺産分割を進めます。遺言書がない場合や無効な場合は、次の遺産分割協議に進みます。

相続財産と負債の把握
相続人が確定したら、亡くなった方の財産(遺産)と負債(借金)のリストを作成します。銀行口座の預貯金残高、不動産(土地・建物)の登記情報、株式などの有価証券、自動車などプラスの財産に加え、住宅ローンや借入金、未払いの税金などマイナスの財産も調べます。これを「財産目録の作成」と呼び、相続手続きの全体像を把握する重要な作業です。例えば、銀行口座は通帳記帳や残高証明で金額を確認し、不動産は権利証や登記簿で名義と評価額を確認します。また、葬儀費用が発生していれば領収書を保管しましょう。相続税の計算時には葬式費用を遺産総額から差し引けるため、記録しておくと役立ちます。反対に、被相続人に多額の借金がある場合など、「財産より借金のほうが多い…」というケースも考えられます。そのような場合、相続人は相続放棄を検討できます。相続放棄とは「一切の財産を受け取らない代わりに借金も引き継がない」という手続きで、家庭裁判所に申述して行います。相続放棄には期限があり、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。例えば、亡くなった方が借金まみれだったと判明した場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申立てをする必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といい、どうするか判断がつかない場合は延長申請も可能です。一方、プラスの財産もマイナスの財産も両方ある場合に、「プラスの範囲内でのみマイナスも引き継ぐ」限定承認という方法もありますが、手続きが難しく相続人全員で行う必要があるため、利用例は多くありません(必要に応じ専門家に相談してください)。

遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)
複数の相続人がいる場合、誰がどの財産を受け継ぐかを決める遺産分割協議を行います。遺言書で分け方が指定されていればその通りにしますが、遺言がない場合は相続人全員で話し合って合意を目指します。法定相続分(法律で定められた相続人ごとの取り分の目安)はありますが、最終的には話し合いで柔軟に決められます。例えば「自宅の土地建物は配偶者が取得し、預金は子ども二人で半分ずつ分ける」といった具体的な取り決めをします。その内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付して作成します。遺産分割協議書は不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなどで必要になる重要書類です。なお、相続人に未成年者がいる場合は注意が必要です。未成年の相続人(例えば幼い子ども)は法律行為ができないため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要が出てきます。特別代理人とは、未成年者の代わりに協議に参加する大人の代理人のことです。例えば、父が亡くなり母と未成年の子どもが相続人となった場合、母と子どもでは利害が対立する可能性があるため、裁判所が第三者を子の代理人に選ぶことがあります。こうした手続きを経て、相続人全員が合意すれば遺産分割協議書を完成させます。
遺産分割の協議

遺産分割の協議に法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに誰が何を相続するか決まっていないと、税金の計算上は一旦「法定相続分どおり」に各人が相続したものとして申告することになります。その後、実際の分割が決まってから修正申告する手間も生じるので、可能であれば早めに協議をまとめるのが望ましいでしょう。また、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停や審判(裁判手続)に進むことになります。相続人間で意見が対立して揉めてしまった時は、早めに弁護士など専門家に相談することも検討しましょう。

各種名義変更と手続き
遺産分割の方針が決まったら、具体的な名義変更の手続きを行います。銀行預金は各銀行で相続手続きを行い、相続人名義の新しい口座にお金を移すか、分配します。銀行では通常、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書などの提出を求められます。何度も戸籍を提出するのは大変ですが、ここで便利なのが法定相続情報証明制度です。この制度を利用すると、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」という書面を1通用意するだけで、銀行や証券会社など様々な手続き先に提出できるため、戸籍の原本を何通も用意する手間が省けます。例えば通常なら10通以上の戸籍謄本を準備して各所に提出するところを、この一覧図の写し1通をコピーして使い回せます。平成29年(2017年)から始まった制度で、手数料は無料です。不動産の名義変更(相続登記)も重要な手続きです。土地や建物など不動産を相続した場合、法務局で所有権の移転登記を申請し、名義人を書き換える必要があります。この相続登記については2024年4月1日から申請が義務化されました。これまでは名義変更は義務ではなく放置されるケースも多かったのですが、法律改正により、「自分が相続人であり、かつ相続によって不動産を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければならないと定められたのです。正当な理由なくこの期限を過ぎると、法務局から催告(督促)が行われ、それでも応じない場合は10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。簡単に言えば「不動産を相続したら3年以内に名義変更をしないといけない」というルールですので、忘れずに対応しましょう。例えば遠方の土地を相続した場合でも、期限までに必ず登記申請を行うようにしてください。なお、この義務化は過去の未登記物件にも遡及適用されるため、以前に相続した不動産でまだ名義を書き換えていないものがある場合も注意が必要です。どうしても管理が難しい土地を相続した場合には、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度という制度も2023年から開始されています。このような特殊なケースについては専門家や法務局に相談してみましょう。

税金の申告と納付
相続が発生すると関係する税金の手続きも発生します。大きく所得税(被相続人の準確定申告)と相続税の2つがあります。まず、亡くなった方(被相続人)の準確定申告(最後の所得税の申告)です。被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに得た所得について、相続人が代わって所得税の申告をします。この申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内(通常は死亡日の翌日から4ヶ月以内)に行わなければなりません。例えば、3月15日に亡くなった方がいれば、その年の1月1日~3月15日までの所得について相続人が計算し、死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。これを怠ると延滞税や無申告加算税など余計なペナルティが発生することがあるので注意しましょう。

法定相続分と指定相続分を理解する
次に相続税です。相続税は、遺産の額が一定の基準を超えるとかかる国税です。ただし心配しすぎる必要はなく、相続税が実際に課税されるのは全体の1割程度です。具体的には「遺産総額 - (借金+葬式費用)=課税価格」が、基礎控除額を超えた場合にのみ相続税の申告・納税が必要になります。基礎控除額とは非課税枠のことで、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」ですmof.go.jp。遺産から借金や葬儀費用を引いた正味の額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません(このケースでは日本全体で見ると約90%以上の方は該当しません)。一方、基礎控除を超える財産を相続した場合には相続税の申告が必要です。相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で決まっています。通常は亡くなった日から10ヶ月以内と覚えておけば良いでしょうnta.go.jp。例えば、1月15日に死亡した場合、11月15日が申告期限となります。申告先と納付先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。期限までに現金一括で納めるのが原則ですが、金銭で納めるのが難しい場合は税務署の許可を得て延納(分割払い)や物納(不動産など財産で納付)の制度を利用することもできますnta.go.jp。相続税の計算は複雑なので、該当しそうな場合は早めに税理士に相談すると安心です。
専門家に依頼できること(行政書士・税理士・司法書士・弁護士の役割)

行政書士(ぎょうせいしょし)
法律に基づく書類作成の専門家です。相続では戸籍の収集代行や相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成など書類面でのサポートを依頼できます。銀行口座の名義変更手続きや自動車の相続手続き(車検証の名義変更)なども代理可能です。遺言書の作成をサポートする行政書士もいます。ただし、行政書士は不動産の名義変更(登記)を行う権限がありませんし、家庭裁判所で行う相続放棄の申立て代理や、相続人同士の揉め事の解決、相続税の相談・申告といった業務はできません。その分、報酬額は他の専門家より比較的低めで済むケースが多いです。例: 「遺産は現金と車だけで不動産はないし、相続人同士も揉めていない」というケースでは行政書士に依頼するとスムーズでしょう。
当所の場合は、司法書士と提携して不動産の登記までフォローさせていただいておりますので、相続不動産がある場合でも安心してご依頼ください。

司法書士(しほうしょし)
登記の専門家で、不動産の相続登記(名義変更)を代行するプロです。相続財産に土地や建物が含まれる場合、司法書士に依頼すれば必要書類の準備から法務局への申請まで任せられます。司法書士も行政書士同様に相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成支援(遺産に不動産がある場合)も行います。さらに、相続放棄や限定承認についても必要書類の作成は対応可能です(※ただし代理人として家庭裁判所に申立てすることはできません)。一方で、遺産分割の争いの代理交渉や遺留分(一定の相続人に保証される取り分)をめぐるトラブル解決は司法書士にはできません。費用は弁護士より安めの場合が多いです。例: 「自宅の土地建物を相続するけれど、相続人同士は争っていない」という場合は司法書士に不動産登記を依頼すると良いでしょう。

税理士(ぜいりし)
税務の専門家です。相続税の申告書作成や税額計算、税務相談を依頼できます。相続財産の評価や節税対策についてもプロの視点でアドバイスしてくれます。遺産が基礎控除内に収まる場合、税理士に依頼せず自分たちで申告不要というケースも多いですが、判断に迷う場合や節税の余地がありそうな場合は相談する価値があります。なお、税理士は税務以外の業務(不動産の名義変更や相続人間の揉め事の解決、家庭裁判所での手続きなど)には対応できません。例: 「遺産が多額で相続税の申告が必要だが、自分で計算するのは不安」という時は税理士に依頼するのが一般的です。

弁護士(べんごし)
法律業務全般の専門家で、相続人同士の紛争解決の代理ができる唯一の士業です。遺産分割の話し合いがまとまらない場合の交渉代理や、家庭裁判所での調停・審判の手続き代理、遺留分をめぐる訴訟、使い込まれた預金の返還請求など、争いに発展したケースでは弁護士の出番です。また、弁護士は相続放棄や限定承認の申立てを代理することもできます。依頼できない業務としては税理士資格のない弁護士は税務申告を扱わない点くらいで、基本的に他の士業ができる書類作成や登記も弁護士自ら行う権限は持っています(もっとも、不動産登記業務は司法書士に任せる弁護士事務所が多いです)。費用は他の専門家より高額になりがちなので、「明確な争いがある場合」に依頼するのが一般的です。例: 「相続人の間で遺産の配分でもめて話し合いにならない」「遺言の有効性を巡って訴訟になりそうだ」といった場合は弁護士に相談・依頼すべきでしょう。

専門家による期限管理の重要性
このように相続手続きではそれぞれの専門家にできることが異なります。必要に応じて適切な士業の力を借りれば、複雑な手続きも安全かつ確実に進めることができます。特に相続税申告が必要なケースでは税理士、不動産がある場合は司法書士、書類作成中心なら行政書士、争いがあるなら弁護士というように使い分けると良いでしょう。ただ、相続の案件によっては複数の分野にまたがる手続きが必要になることも多いです。例えば「不動産も現金もある大きな相続で、分割方法でも多少意見の対立がある」というような場合、一人の専門家だけでは対応しきれず、司法書士・税理士・弁護士がそれぞれ活躍する場面が出てきます。
まとめ

初めて相続手続きを経験する方に向けて、流れと注意点を解説しました。重要なのは、期限がある手続き(相続放棄は3ヶ月、準確定申告は4ヶ月、相続税申告は10ヶ月、相続登記は原則3年以内)を見逃さずに進めることです。それぞれ必要な書類を早めに集め、計画的に対応しましょう。また、無理に全てを一人で抱え込まず、状況に応じて専門家のサポートを受けることも検討してください。専門家に依頼すれば費用はかかりますが、その分ミスやトラブルを防ぎ安心して手続きを進められます。
当所では、お客様のニーズに合わせて、各専門家と連携する事で、相続手続きの窓口を一本化することができます。
相続手続きをご自身でやるのはご不安な方は、是非お気軽にお問い合わせください。



